未来のじぶんに、ちょっと先の気づきを
自分らしい働き方を見つけるためのコラム
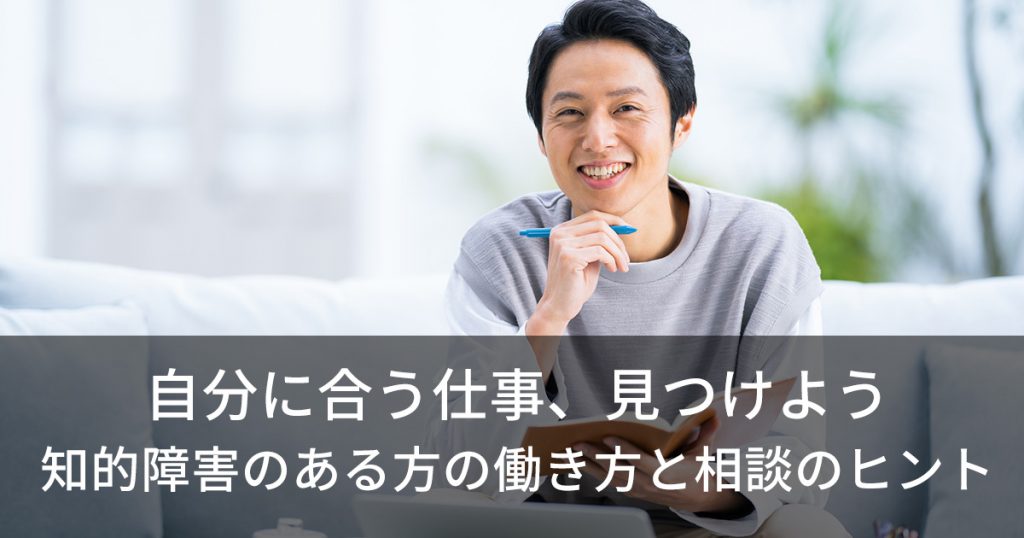
知的障害があり「はたらけるのか」「どのような仕事ができるのか」といった悩みを抱えている方もいるでしょう。現在、障害者全体の社会参加は進んでおり、知的障害のある方も仕事で活躍するチャンスが広がりつつあります。今回は、知的障害者の就労の現状を踏まえ、向いている仕事を探すノウハウを紹介します。
就労の不安を相談できる場—キャリア共創コミュニティ「あしたのあるきかた」に登録>>
知的障害のある方の仕事の実態
厚生労働省の調べによると、2023年時点で従業員規模5人以上の事業所に雇用されている知的障害者は推定27万5,000人でした。そのうち、重度知的障害のある方が11.8%です。正社員として勤務しているのは20.3%であり、有期契約の非正規雇用が最も多いという結果でした。また、障害者雇用において1カウントと計上される週30時間以上はたらいている方が最も多く、全体の64.2%を占めます。
職業別にみると、最も多いのがサービスの職業、次いで運搬・清掃・包装等、販売と続きます。平均勤続年数は9年1月となっている一方で、1ヶ月の平均賃金は13万7,000円と、その他の障害のある方と比べ低い水準です。
知的障害のある方の働き方

知的障害がある方の働き方には、一般枠ではたらく以外に、次の2つの選択肢があります。
- 一般企業における障害者雇用枠での就労
- 福祉的就労
一般企業における障害者雇用枠での就労
障害者雇用枠とは、障害者手帳を取得している方を対象とする一般企業の就労の求人です。障害があることを前提としているため、特性への理解や適切な合理的配慮が得やすく、無理なくはたらける可能性が高いといえます。ただし、求人数や募集人数が少ないことも多く、特に事務系などの人気の職業は狭き門となっていることもあるようです。
福祉的就労
福祉的就労とは、障害のある方が、障害者就労施設ではたらくことです。具体的には、就労継続支援A型もしくはB型の事業所に勤務します。
そのうちA型事業所は、就労自体は可能ではあるものの、一般企業ではたらくのが困難な方を対象とする職場です。利用には一定の条件を満たす必要がありますが、事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金をもらいながら、一般就労への移行を目指します。
一方B型は、一般企業およびA型事業所ではたらくのが困難な方や年齢が50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方などを主な対象とする事業所です。特性や体調に合わせてはたらきつつ工賃を受け取れますが、雇用契約に基づかないため対価が低い傾向にあり、一般的な最低賃金の水準に満たないこともあります。
【分類別】知的障害のある方に向いている仕事
続いて、知的障害の程度別に、向いている仕事や働き方を説明します。
軽度・中等度の知的障害がある方
軽度の知的障害とは、IQ51〜70程度の方が分類される区分です。一方、中等度の知的障害とは、IQ36〜50程度の方が分類されます。特性に差はありますが、いずれの分類でも、身の回りのことや簡単な作業・学習はある程度できることが多いです。
ただし、複雑な文字の読み書きや計算、暗算などの高度な作業は行えません。また、物事・指示の理解や判断力にも限りがあるため、その場に応じた状況判断や臨機応変な対応は困難です。こうした理由から、一見すると健常者と見分けがつきにくい方でも、一般枠で就職すると負担やストレスを感じやすいでしょう。
軽度・中等度知的障害のある方は、軽作業やデータ入力など変化の少ないルーチンワーク中心のデスクワークがはたらきやすいといわれています。イラストやデザインなど得意なことがある方は、それが活かせる仕事を目指すのもおすすめです。一人ひとりの特性に合わせ、適切な支援と配慮を得てはたらける職場を選びましょう。
重度・最重度の知的障害がある方
重度の知的障害とは、IQ21〜35程度の方が分類される区分です。IQ20以下では、最重度に分類されます。一般的に、重度もしくは最重度の知的障害があると、自分の力だけで日常生活を送るのは困難で、周囲のサポートが必要です。言葉や運動能力の発達に遅滞がみられ、文字や数字でのコミュニケーションは難しい傾向にあります。
とはいえ、絵やカード、身振り手振りでの意思疎通は可能です。一般企業や障害者雇用での単純な軽作業や定型の業務なら行える可能性があるほか、就労継続支援事業所に通所する方もいます。
知的障害のある方に多い仕事・就活に関する困り事
ここでは、知的障害の特性から、仕事や就職活動においてよくある困り事と、その対処法をみていきましょう。
仕事が覚えられない
知的障害があると、仕事の手順やルール、マナーがうまく覚えられない方も少なくありません。注意されても理由がよく理解できなかったり、見通しが立てられなかったりして、努力してもミスを繰り返してしまうこともあります。
知的障害のある方が仕事をスムーズに覚えるためには、マニュアル整備や、業務上で使用する備品を判別しやすいようラベルを付けるなどの配慮が必須です。工夫次第では改善が見込める可能性もありますが、障害特性により自分の努力だけでは対処できない範囲もあるため、必要とするサポート内容を明確化しておく必要があります。
仕事が続かない
知的障害のある方は、仕事内容やルール、ビジネスマナーなどの理解が難しく、仕事を継続できないと悩む方も珍しくありません。いざはたらき始めてみると、思っていた内容と違い、短期間で退職することになったというケースも多い傾向にあります。
ミスマッチの主な原因は、リサーチ不足です。自己理解と企業・業界研究を深め、自身の特性や希望と擦り合わせることで、納得のいく就職が実現しやすくなります。
給料が低い
知的障害のある方の1ヶ月の平均賃金は低水準です。給料が低すぎると、はたらいてもやりがいが感じられないという方も多いでしょう。
状況を改善するには、仕事が進めやすくなるよう特性に応じた工夫を凝らすほか、興味・関心が持てる新たな仕事への転職にチャレンジすることが選択肢となります。
知的障害のある方が仕事や就活で悩んだときは?

ここからは、知的障害のある方が仕事や就職活動で悩んだときの解決策を紹介します。
公的な相談窓口を利用する
障害のある方の就職活動や就労の悩みなどに関しては、専門の公的機関で相談できる体制が整えられています。例えば、全国の「ハローワーク(公共職業安定所)」には障害者専門窓口が設置されており、障害のある方へ向けたさまざまなサポートが受けられます。地域の公的機関と連携した包括的な支援が受けられるため、仕事や就活に関する悩みを解決するヒントが得られるでしょう。
就労移行支援事業所へ通所する
「就労移行支援」とは、一般企業での就労へ向けた訓練が受けられる制度です。原則として最長2年の間、生活指導を通して就労の基礎力となる職業準備性が身につけられるほか、就労に役立つ技能の習得や実習・職場体験などの一般就労に近い形での訓練でスキルアップを図り、一般企業での就業を目指します。
障害者向け転職・就職エージェントのサポートを受ける
「障害者向け転職・就職エージェント」とは、障害者手帳を取得している方を対象に、求人の紹介と就活支援を行うサービスです。プロのキャリアアドバイザーが付き、ヒアリングした内容を基に個々の特性に合わせた求人の紹介および就職活動のトータルサポートが受けられるため、長く安定してはたらける可能性が高まるでしょう。
障害者向け転職支援コミュニティで仲間を探す
仕事や就活に関する困り事を抱えているなら、同じ障害や目標、悩みを持つ仲間と交流してみるのも一つの方法です。「障害者向け転職支援コミュニティ」に登録すれば、多くの仲間とつながれます。学習コンテンツをアップしているサイトもあり、うまく活用すれば情報収集と学び、相談先が同時に得られます。悩みを話すだけでも気持ちが軽くなり、前向きになれるので、気軽に利用してみるとよいでしょう。
仕事や仕事探しのストレスは一人で抱えず誰かに相談を!
知的障害のある方は、できること・できないことが個々で大きく異なることから、知的障害の特性を正しく理解して受け入れ、特性に合わせた仕事に就くことが大切だといえます。効率的な仕事探しとコツを押さえた就活準備を進めるためにも、支援サービスも利用しつつ、個別の対策を立てましょう。
また、仕事や仕事探しでストレスを抱えているなら、障害者向け転職支援コミュニティ「あしたのあるきかた」で相談してみませんか。仲間とつながり、話をすることで不安な気持ちが和らぐうえ、同じような経験のある方から有益なアドバイスが得られるかもしれません。ぜひお気軽にご登録ください。
就業意欲のある障害者向けの
コミュニティサイト
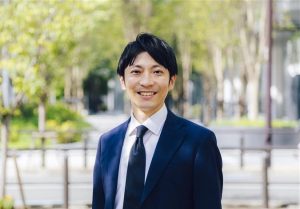
戸田 幸裕
上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタント、障害者職業生活相談員





