未来のじぶんに、ちょっと先の気づきを
自分らしい働き方を見つけるためのコラム

障害の有無にかかわらず「ホワイト企業」ではたらきたいと考える方は多いでしょう。ただし、障害のある方にとって、給与や休暇といった一般的な要件を満たすだけではホワイト企業とはいえません。今回は、障害者雇用におけるホワイト企業の定義と、障害のある方がはたらきやすい転職先を見極めるポイントを解説します。
→ 仲間と情報交換&専門スタッフに相談—コミュニティ「あしたのあるきかた」に無料で登録する>>
「ホワイト企業」の一般的な定義
まず、障害がある方にとっての「ホワイト企業」とはどのような会社なのか、一般的な定義を明らかにしておきましょう。
労働条件が適正で受け入れ環境が整っている
ホワイト企業は、勤務時間や休暇が適正に設定されています。適正な労働時間とは、1日8時間以内、週40時間以内、残業時間は月15時間以内が一般的な目安です。休日は週休2日、月8日以上に設定されていることが多く、有給休暇は1年間で平均10日以上取得していることが目安となります。また、休暇や各種手当、社内設備などの福利厚生も充実している傾向にあり、心身および経済的な負担を軽減する工夫がなされているほか、給与や賞与も好条件の求人が多いです。
離職率が低い
ホワイト企業は、従業員を大切にし、はたらきやすい環境を整えているため、離職率が低い傾向にあります。なお、企業ごとの離職率は、東洋経済新報社の「就職四季報」でチェックできます。ただ、離職率を公表していない企業も多いため、インターネット上の評判やクチコミも確認しておくとよいでしょう。
従業員教育に力を入れている
ホワイト企業の多くは、人材こそ企業の資産だという観点から、従業員教育に力を入れています。また、CSR(企業の社会的責任)の立場からも、従業員一人ひとりの個性を尊重し、それを伸ばす努力を惜しみません。キャリアパスを明確に示し、セミナーや講座、勉強会を定期的に開催したり、資格取得の奨励制度を設けたりするなど、従業員の成長を積極的にサポートしています。
経営状況が健全な企業である
ホワイト企業かどうかを見極めるにあたって要チェックポイントとなるのが「会社の経営状況」です。一般的に、企業の規模が大きいほど経営が安定しており、雇用数も多い傾向にあります。またCSRの観点からも、障害者雇用に積極的で障害者雇用枠の求人件数も比較的豊富といえるでしょう。企業としての将来性も高いため、転職すれば長く安定してはたらける可能性が高まります。
安全衛生優良企業の認証を取得している
「安全衛生優良企業」とは、労働者の安全と健康を確保する取り組みや環境整備を積極的に行っている企業に与えられる認証です。過去3年間に渡って労働安全衛生関連の重大な法違反がない企業が取得できることから、従業員がはたらきやすいよう配慮していることの証だといえます。「認証がない=ブラック企業」というわけでは決してありませんが、企業の方針を判断する一つのポイントです。
障害者の採用実績が豊富なホワイト企業を見極めるポイント
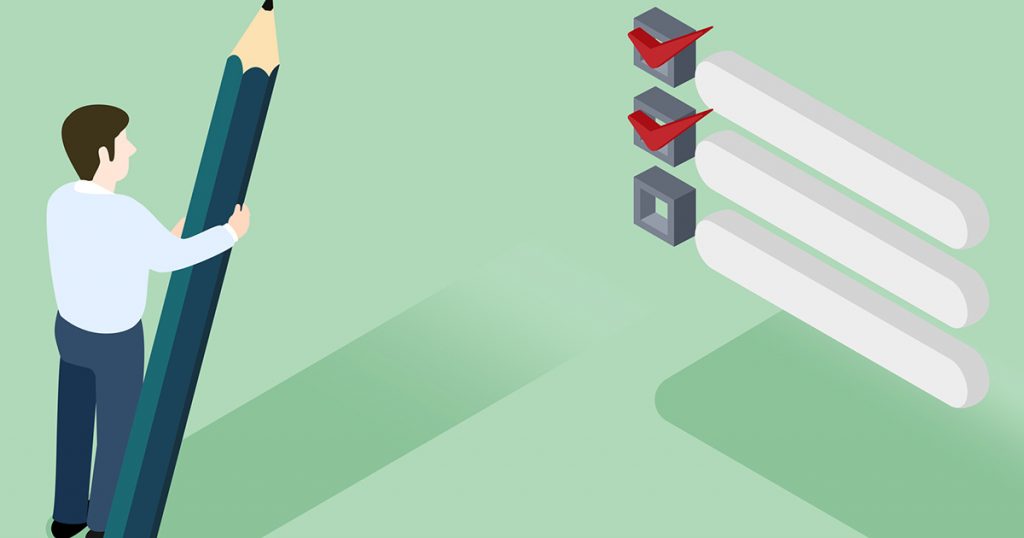
次に、障害者雇用に積極的で、採用実績も豊富なホワイト企業を見極める2つのポイントを説明します。
障害者の実雇用率
障害者の実雇用率の高さは、障害者雇用に積極的かどうかを見極める指標の一つです。実雇用率とは、企業の達成目標として設定されている法定雇用率に対し、実際に障害者を雇用している割合を指します。
実雇用率が高いからといって必ずしもホワイト企業とは言い切れないものの、採用されやすく、独自の取り組みで障害者の就労をサポートしている可能性が高いです。なお、障害者の実雇用率については東洋経済新報社「CSR企業総覧(雇用・人材活用編)」で毎年ランキングが公表されているので、参考にしてみるとよいでしょう。
合理的配慮のレベル
障害のある方がはたらくうえで、適切な合理的配慮は必須条件です。求めるサポートの内容や程度は人それぞれなので、一辺倒なサポートではなく、個々の特性に合わせたきめ細やかな配慮が求められます。実際にどんな障害のある方がはたらいていて、それぞれどのような配慮があるのかをチェックすることで、企業の障害者雇用に対する意識が伺えます。
また、就業中に困ったときのサポート体制や、相談窓口があるかどうかもチェックしましょう。とはいえ、内部情報を公開していない企業も多いため、転職エージェントのような就労支援サービスに相談してみることをおすすめします。
障害者がホワイト企業の求人を探す方法
続いて、障害のある方がホワイト企業の求人を探す4つの方法を紹介します。
障害者専門の転職エージェントに登録する
「障害者専門の転職エージェント」とは、障害のある方の仕事探しをサポートするサービスです。障害者雇用に精通した専門のキャリアアドバイザーとのカウンセリングを通し、特性に合わせてはたらける求人を紹介してもらえます。大企業や優良企業の求人のほか、一般公開されない非公開求人の紹介も受けられる点が魅力です。求人票には書かれていないような内部情報も提供してもらえるため、障害のある方がはたらきやすいホワイト企業を見つけやすくなるでしょう。
特例子会社を選択肢に入れる
障害のある方には「特例子会社」も選択肢の一つです。特例子会社とは、障害者の安定雇用を目的として設立された企業・事業所として厚生労働省の認可を受けた子会社もしくはグループ会社を指します。個々の特性に応じた配置や環境調整などの配慮がなされるため、障害のある方が比較的安定してはたらけます。さらに、親会社勤務と同等の社会的な信頼感や給与水準、福利厚生などの待遇が得られる場合もあります。特例子会社の数は2024年6月1日時点で614社、378グループあるといわれています(出典:厚生労働省「特例子会社」制度の概要)。会社数や雇用されている障害者の数は年々増加しており、就業のチャンスは今後ますます増える見込みです。
企業説明会や採用イベントで実際の雰囲気を体感してみる
障害のある方が転職後の定着率を高めるには、企業とのマッチングが肝心です。説明会やオープン・カンパニーに参加すれば、パンフレットやインターネット、求人票などからは分かりにくい、詳しい企業情報が得られます。実際にはたらく人の様子や雰囲気を肌で感じられ、自身との相性がチェックできるでしょう。また、人脈づくりや内定獲得へ向けて共に頑張る仲間に出会えることもあるので、積極的な参加をおすすめします。
障害者向け転職支援コミュニティで情報交換する
「転職支援コミュニティ」とは、転職や仕事探しをしている方が集まり、意見や企業の情報、自身の体験などを共有するためのプラットフォームです。障害者向けのサイトもあり、企業の情報や選考を受けたリアルな経験・感想が聞けるほか、悩みを気軽に相談し合いながら、安心して転職活動が進められます。同じ目標・目的を持つ仲間と交流することで、気持ちが軽くなるほか、悩み解決の糸口が得られるかもしれません。転職活動に関する学べるコンテンツを配信しているケースもあり、うまく活用すれば障害者雇用の疑問や不安が解決できるはずです。
転職活動のヒントが見つかるコミュニティ「あしたのあるきかた」。ぜひ登録してみてください!
障害者がホワイト企業への転職を成功させるコツ

ここからは、障害者雇用に積極的なホワイト企業へ転職し、長く安定してはたらき続けるため、転職活動の際に押さえるべき3つのポイントを説明します。
自己分析を深める
仕事探しや就業における優先順位は、人それぞれ異なります。そのため、無理なくはたらけて、自分らしく活躍できる仕事を見つけるには、深い自己理解が大切です。特に障害のある方は、個々の特性・症状や必要な配慮事項を明確化し、周囲にも理解してもらうことが求められます。実際に、自分のことをしっかりと理解できている人ほど、満足のいく転職を実現しているという調査結果も存在します。自己理解を深めることは、安定就労を実現させるためのファーストステップです。応募書類や面接で特性や配慮事項を伝える際にも、自己対処を踏まえたポジティブな伝え方ができるようになるので、面接官に好印象が与えられるでしょう。
職業準備性を高める
「職業準備性」とは、はたらくにあたって必要となる基礎的な能力の総称です。具体的には「決まった時間に起きる」「時間に間に合うようスケジュールを立てる」「適切なコミュニケーションを取る」「職業適性を身につける」など多岐に渡ります。障害のある方は、その特性から、自分の努力だけでは職業準備性を高めるのが難しいと悩んでいる方も少なくありません。障害の専門知識を持つプロや、同じ悩みを克服した仲間の意見を聞くことが、職業準備性を高める第一歩です。
面接で逆質問をする
採用面接や説明会では、企業から応募者へ「質問はありませんか?」と尋ねる「逆質問」が行われることがあります。逆質問は、企業の姿勢や実際の職場環境を深く知る絶好の機会です。Webサイトやパンフレット、全体説明などでは分からない情報や、応募者や従業員に対する向き合い方が伺えます。節度やマナーを守って、積極的に質問してみるとよいでしょう。
障害者が自分にとってのホワイト企業を見つけるには情報収集が重要!
障害のある方にとって、ホワイト企業の定義は一概にはいえません。大切なのは、条件・待遇面だけではなく、自身の障害特性とのマッチングです。どのような企業ではたらきたいのかを明確化し、希望の条件に合う職場こそ、あなたにとっての「ホワイト企業」だといえます。
自分らしくはたらけるホワイト企業を見つけるには、正確な情報をたくさん集めることが重要です。自力で情報収集するのは容易ではないため、プロのキャリアアドバイザーの意見を仰ぐほか、同じ目的・立場の仲間が集まる転職支援コミュニティを利用してみてはいかがでしょうか。
「あしたのあるきかた」では、障害のある方がオンラインで交流できる場を提供しています。情報の共有やちょっとした悩み相談など転職活動におけるさまざまなヒントが得られる気軽なプラットフォームを、ぜひ活用してみてください。
就業意欲のある障害者向けの
コミュニティ「あしたのあるきかた」
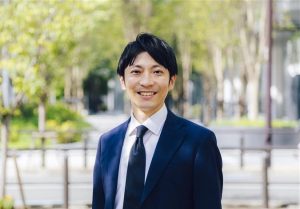
戸田 幸裕
上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタント、障害者職業生活相談員






